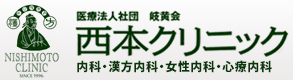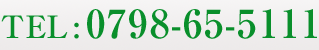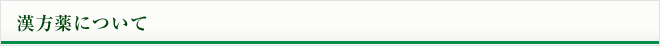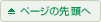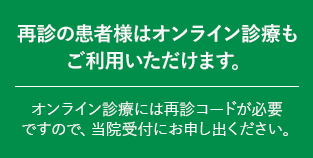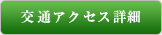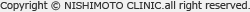生姜、山椒、小豆、百合根、ニンニク、ヤマイモ、紫蘇の葉……。おなじみの食材ばかりですが、実は、これらはすべて漢方薬の材料(生薬)です。
生姜、山椒、小豆、百合根、ニンニク、ヤマイモ、紫蘇の葉……。おなじみの食材ばかりですが、実は、これらはすべて漢方薬の材料(生薬)です。
漢方薬というと、タツノオトシゴや鹿の角など、特別なものばかり連想する人がいるかもしれませんが、実は、私たちがふだん食べているものもたくさん材料として使われています。例えば、風邪薬の『桂枝湯』。桂枝、白芍、炙甘草、生姜、大棗という5種類の生薬から成っていますが、このうち、まず、主薬である桂枝はシナモン(ただし、食用のシナモンは幹皮で、桂枝は若い細枝かその樹皮)ですし、生姜は、食べる生姜と全く同じものです。そして、大棗は果物のナツメ、炙甘草は、甘味料として使われる甘草をハチミツとともに炒ったもの、と、白芍以外はすべて食物といえるものばかりです。
そもそも、「薬食同源」という言葉があるように、薬と食べ物ははっきり区別できるものでもないのです。別の言い方をすれば、食べ物の中でも、薬効が強いものが薬ということになります。
だからといって、「食べ物に近いから、効き目が穏やか」「自然のものだから、体に優しい」というわけではありません。熱症状があるときに温める薬を飲むと、かえって症状を悪化させることでも分かるように、「薬」も使い方を間違えれば、「毒」になってしまいます。そういう意味では、食べ物も毒になる可能性があるわけです。これは、偏食が体に及ぼす影響を考えても分かることかもしれません。
ただ、植物から有効成分だけを抽出した西洋薬と比べれば、植物そのものを使う漢方薬のほうが、効き目が穏やかで、副作用も起こりにくいことは確かです。
このほか、漢方薬独特の加工法として、生薬をあぶったり、乾燥させたりすることで、毒性を消失させたり、生なまとは異なる薬効を引き出す「炮製」という方法もあります。
例えば、「附子」という生薬は、もともと非常に毒性が強い植物です。別名「トリカブト」といえば、もうお分かりでしょう。殺人事件にも使われるこの劇薬も、炮製することで毒性のない薬に生まれ変わり、『
また、先ほどの甘草のように、ハチミツとともに炒る「蜜炙」も炮製のひとつです。生の甘草は涼性で、熱をさます作用がありますが、蜜炙することで温性に変わり、胃腸の気を補う作用も生まれます。
ちなみに、加工法によって作用が違うのは、食べ物でも同じです。例えば、生では「寒性」の大根も、煮たり蒸したりすることで、それほど体を冷やさない性質に変えることができます。つまり、二日酔いやのどの痛みには大根おろし、寒い冬にはおでんやブリ大根がいいということになります。また、一般的に、生ものは体を冷やし、揚げ物や直火焼きなど、熱を直接加える調理法は、体に熱を生むと考えられています。体を冷やしすぎるのも、熱しすぎるのもいいことではないため、養生食では、煮物や蒸し物が勧められることになります。こんなことも考えに入れながら献立を決めるのも、たまにはいいかもしれません。
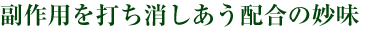
漢方薬は、何種類かの生薬を組み合わせて作られています。これは、単なる「たし算」ではありません。短所も長所もある生薬を合わせることで、生薬の長所が「かけ算」的に強化されることもあれば、毒性や強すぎる作用を中和する「引き算」の要素もあります。この組み合わせの妙があるからこそ、複雑な病変にも対応することができるのです。
では、人参、白朮、茯苓、炙甘草という四つの生薬から成り立つ『
また、別の面から四君子湯の構成をみると、「人参+炙甘草」は体に潤いを与え、「白朮+茯苓」には、体の水分をとりのぞく作用があることが分かります。このように、あえて相反する作用の生薬を組み合わせることで、潤しすぎず、乾かしすぎずという絶妙なバランスが生み出されているのです。さらに、炙甘草は、全体をうまくまとめる「和」の働きも発揮しています。
非常にバランスのいい薬ですが、この四君子湯がそのまま用いられることはあまりありません。病気というのは、体のバランスが崩れている状態なので、凸に凹を組み合わせるような治療が必要です。つまり、四君子湯のようにバランスのとれた薬ではなく、ある意味でアンバランスな薬のほうが合うわけです。
四君子湯の仲間で、最も汎用性があるのは「六君子湯」という漢方薬です。これは、半夏、陳皮、生姜、大棗を加えることで、「脾」だけでなく「胃」も考慮し、また、消化吸収力の低下によって生まれた水毒・食毒をとりのぞく作用が強くなっています。
このように、配合の妙から成る漢方薬ですが、臨床に用いる際には、その人の体質や年齢、病態によって、臨機応変にさじ加減をする必要があります。特に、重篤な病気には、「その法(ルール)にしたがいて、その方(方剤そのもの)にこだわらず」というように、適切に配合を変化させることが大切だといわれています。

 この漢方薬の「さじ加減」について、もう少し詳しく説明しましょう。「○○湯」「○○散」といった基本方剤の中に、例えば、「大黄」という生薬が入っていたとします。大黄は便秘の薬で有名なことでも分かるように、おなかの熱をとりのぞいて瀉下する作用があります。そのため、基本方剤は使いたいけれど、便秘はしていないという患者さんの場合、大黄の下剤としての作用がじゃまになることもあるわけです。
この漢方薬の「さじ加減」について、もう少し詳しく説明しましょう。「○○湯」「○○散」といった基本方剤の中に、例えば、「大黄」という生薬が入っていたとします。大黄は便秘の薬で有名なことでも分かるように、おなかの熱をとりのぞいて瀉下する作用があります。そのため、基本方剤は使いたいけれど、便秘はしていないという患者さんの場合、大黄の下剤としての作用がじゃまになることもあるわけです。
この場合、大黄をとりのぞくという方法以外に、酒に浸してあぶった(酒炙)酒大黄に変えるという方法もあります。大黄を酒炙すると、下剤としての作用が弱くなるだけでなく、血をめぐらせる作用が生まれます。そのため、同じ便秘でも、オ血が原因になっているような患者さんには、この酒大黄を入れた方剤のほうが向いているということになります。
ただし、このようなさじ加減が可能なのは、生薬を自由に組み変えることができる煎じ薬だけです。「エキス剤」と呼ばれる粉薬は、他の方剤を代用するしか方法はありません。また、エキス剤の種類は、各メーカーから発売されているものを合わせても、せいぜい百数十種類と数が少ないため、いつでも症状にぴったり合った処方がみつかるとは限らないのです。
もちろん、エキス剤にもメリットはあります。エキス剤は、煎じた漢方薬から水分をとって粉末にしたもので、デンプンなどの賦形剤を加えているために、湿りにくく、かつ飲みやすくなっています。インスタントコーヒーのようなもの、といえば分かりやすいかもしれません。エキス剤の利点は、何より煎じる手間がいらないことです。お湯に溶いて飲めば、煎じ薬と同じような効果を得ることができます。
煎じ薬との違いは、ちょうどオーダーメイドと既製服のようなものといえます。既製品でも、品質がよく、サイズがぴったり合えば、特にオーダーする必要がないように、そのときの体の状態に合えば、エキス剤でも十分に対応することができます。ただ、費用についていえば、オーダーメイドと既製服のような違いはありません。健康保険が使える病院なら、エキス剤より煎じ薬のほうが安くつくことも多いのです。
ちなみに、私のクリニックでは、患者さんの症状と体質によって煎じ薬とエキス剤を使い分けています。また、ふだんは煎じ薬を飲んでいる人でも、「最近、忙しくて薬を煎じる暇がない」「旅行に行くので、煎じ薬は無理」などという場合には、エキス剤に変えることもあります。逆に、「煎じ薬はめんどう」という患者さんでも、症状が複雑でエキス剤では対応しきれない場合には、その旨を説明して、煎じ薬を使ってもらうことになります。
現在、病院で使われる漢方薬は、ほとんどがエキス剤か煎じ薬ですが、中には生薬を細かい粉末にして合わせたものもあります。これは、「散剤」と呼ばれる伝統的な製剤で、エキス剤と異なり、消化管に入ってからゆっくりと有効成分が溶け出すため、作用が長続きするというメリットがあります。急性疾患には不向きですが、慢性病で長期服用する場合などには有効です。最近、西洋薬でも、体に入ってからゆっくり溶け出す「徐放剤」が開発されていますが、漢方の世界では、すでに何千年も前から薬の作用時間に対する工夫がなされていたわけです。
もうひとつ、散剤には生薬が直接消化管に作用するという特徴があります。胃の痛みなどに用いられる『
なお、安中散の「散」の字でも分かるように、漢方薬の最後の文字は、その薬の飲み方を意味しています。例えば、今では煎じ薬として服用される『